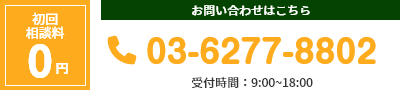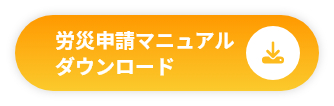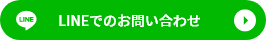安全配慮義務違反とは?
安全配慮義務とは、労働者の生命・身体・健康が害されることがないように配慮する義務であり、使用者(会社)が労働者に対して負う義務です。
具体的には、労働災害が発生しうるリスクを発見し、そのリスクを事前に予防することを内容とします。
会社がこの安全配慮義務に違反すると、その違反が原因で労働者に生じた損害について賠償する義務が発生することになります。
安全配慮義務違反と損害賠償
労働災害に遭われた労働者は、労災保険を利用して労災保険給付を受給することになります。
しかしながら、労災保険給付だけでは、実際に被った損害を補償しきれないことが大半です。
使用者(会社)に安全配慮義務違反が認められれば、この補償しきれない損害の賠償を求めることができるのです。
安全配慮義務の法的根拠と適用範囲
安全配慮義務は、従来は、信義則(民法第1条2項)に基づき労働契約に付随する義務として判例で認められていましたが、2007年に制定された労働契約法により明文化されました。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
なお、ここに定める「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。
また、「必要な配慮」は、一律に定まるものではなく、労働者の職種、労務内容、労務提供場所などの具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
安全配慮義務の適用範囲
上記の労働契約法第5条は、労働契約を結んだ使用者と労働者の間に適用されますから、労働契約の当事者ではない事業者が安全配慮義務を負うことはありません。
しかしながら、直接の労働契約関係にはない次のような場合でも、安全配慮義務が認められる場合があります。
元請と下請
元請と下請という請負関係の場合、下請事業者は独立した立場で請負業務を行いますから、原則として、元請事業者が下請事業者の労働者に対して安全配慮義務を負うことはありません。
しかし、下請事業者の労働者と元請事業者との間に「特別の社会的接触の関係」が認められる場合(例えば、下請事業者の労働者が元請事業者の管理する設備、工具等を用い、元請事業者から直接指揮監督されている場合)には、元請事業者が下請事業者の労働者に対し安全配慮義務を負う場合があります。
発注者と個人事業主
個人事業主も独立した立場で業務を行いますから、原則として、発注者が個人事業主に対して安全配慮義務を負うことはありません。
しかし、業務の遂行に際して、個人事業主が発注者の指揮監督を受けていた場合には、労働契約に準じるような使用従属関係があったとして安全配慮義務が認められる場合があります。
派遣先と派遣労働者
労働者派遣では、派遣労働者は、派遣先の設備や器具を使用し、派遣先の指揮命令に従って就業するため、派遣先は、派遣労働者に対し安全配慮義務を負います。
また、派遣元も、派遣労働者に対して安全配慮義務を負っています。そのため、派遣元が派遣先の安全衛生管理が徹底されていないことを知りつつ放置しているといった場合は、安全配慮義務違反となります。
出向元と出向先
在籍出向では、出向労働者は、出向元・出向先の双方との雇用契約関係が認められるので、出向元・出向先の双方が安全配慮義務を負います。
安全配慮義務の具体的な内容
安全配慮義務の内容は労働者の職種や労務内容の具体的な状況に応じて異なりますが、大まかには以下のように分類することができます。
物的施設の管理に関する義務
労務を提供する際に使用する場所、施設、器具などを管理するにあたり安全策を講じ、労働者の生命・身体などを危険から保護するよう配慮すべき義務です。
施設や器具の整備や点検のほか、事故の要因となりうる作業環境を確認し、必要な対策を実施することなどがこれに当たります。
人的組織の管理に関する義務
労働者や組織を適切に管理し、労働者の生命・身体などを危険から保護するよう配慮すべき義務です。
労働者に対する安全教育の実施、労働者の安全を脅かす行為に対し適切な注意・指導、有資格者や安全監視員等の人員配置などがこれに当たります。
健康配慮義務
労働者の健康状態を把握し、これに応じて業務の軽減などの適切な措置を講じて、労働者の健康に配慮する義務です。
適切な頻度で健康診断を実施したり、必要に応じて、労働内容の変更、労働時間の短縮などの適切な措置を講じることなどがこれに当たります。
職場環境配慮義務
働きやすい良好な職場環境を維持する義務です。
作業環境などの物理的な面の環境を整えることに加え、職場でハラスメントやいじめが生じないよう十分な防止措置を講じたりすることもこれに当たります。
どのような場合が安全配慮義務違反になるのか
安全配慮義務違反があるかどうかは、事案に応じて個々具体的に判断しますが、一般化すると、使用者(会社)側に、予見可能性と結果回避可能性の両方があったときに、安全配慮義務違反となるといえます。
①予見可能性
労働者の心身の安全が害される可能性を使用者が予見できたことをいいます。
例えば、以下のような場合には、予見可能性があるといえます。
・工作機械の整備不良があれば誤作動が起こり、労働者がけがをする可能性がある
・受動喫煙によって健康が害される可能性がある
・長時間労働により心身が害される可能性がある
他方、以下のような場合には、予見可能性がないとされる可能性があります。
・想定される自然災害への備えはしていたが、想定を超えた自然災害が生じた
・持病などをもたない従業員が通常であれば心身障害が生じない程度の業務に従事していたが、突発的な疾患が生じた
②結果回避可能性
①で予見できた労働者の危険を、会社が適切な行動をとれば回避できたことをいいます。
結果回避可能性があるのは、例えば以下のような場合です。
・工作機械の整備はきちんと行っており、マニュアルも備えていたが、労働者に対する安全管理教育が不十分だったため、事故がおきた
・就業規則を超えた過度の残業が行われており、使用者側もそれを知りえたにもかかわらず放置したため心身が害された
・ハラスメント相談窓口がなく被害を訴えられなかったため、心身が害された
他方、以下のように、社会通念上相当と評価される措置を講じたにもかかわらず損害が発生したような場合は、結果回避可能性がないとされる可能性があります。
・工作機械の整備はきちんと行い、マニュアルも備え、労働者に対する安全管理教育を十分に行っていたにもかかわらず、事故がおきた
・特別な事情がないのに、適切に管理された建物内の階段で足を踏み外してけがをした
安全配慮義務違反で会社に損害賠償で訴える方法
(1)「会社を訴えたい」と考えている被災労働者の方は多いと思います。
どのような場合に会社を訴えることができるか?
その答えは、上記のとおり、会社に安全配慮義務違反がある場合です。
したがって、「どの点に会社に安全配慮義務違反が認められるか」という点がポイントなります。
ここでは、事実の抽出、立証の方法、法律構成といった専門的な過程を踏んでいくことになり、法律専門家以外ではなかなか困難な作業です。
「会社を訴えたい」と考えている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。【03-6277-8802】
(2)弁護士に相談し、損害賠償が可能であると弁護士が判断した場合、まずは、会社側と示談交渉を行うことが一般的です。
示談交渉でまとまれば良いのですが、会社側・労働者側の双方が妥協点を見いだせないと訴訟を提起して、訴訟手続の中で解決を図ることになります。
ぜひ弁護士にご相談ください。
冒頭に述べたとおり、労災保険給付では、十分な補償が得られない場合があります。
会社に対する損害賠償請求が可能かどうか、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
初回相談料は無料です。
お一人で悩まずに、まずは、ご相談ください【03-6277-8802】。メールやLINEでも相談可能です。

依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!