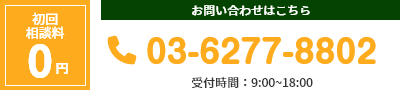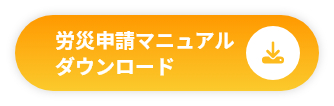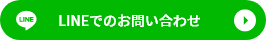精神疾患の労災認定
どのような場合に、精神疾患について労災認定されるのかについては、こちらをお読みください
精神疾患の症状固定
症状固定とは
労災保険における「症状固定(治ゆ)」とは、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上⼀般に認められた医療を⾏っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。
「症状固定」(治ゆ)となった後は、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付の支給は打ち切られます。
精神疾患の症状固定
以上のことは、精神障害についても同様です。
心理的負荷による精神疾患は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治し再度の就労が可能となる場合が多いですが、就労が可能な状態でなくとも、症状固定(治ゆ)の状態にある場合もあります。
精神疾患の治療方法と治療期間
治療の方法
精神疾患に対する治療法は、身体的な治療法と、精神療法(心理療法)のいずれかに分類できます。
身体的な治療法としては、薬物療法と電気けいれん療法のほか、脳を刺激する治療法(経頭蓋磁気刺激療法や迷走神経刺激療法など)などがあります。
精神療法的な治療法としては、精神療法(個人療法、集団療法、家族療法、夫婦療法)、行動療法(リラクゼーション訓練や曝露療法など)、催眠療法などがあります。
主な精神疾患では、薬物療法と精神療法を併用することで、一方を単独で用いるより高い治療効果が得られるとされています。
精神疾患の治療は長引くことが一般的
なぜ精神疾患の治療は長引くのか。
幾つか要因がありますが、主立った事由を列挙すると以下のとおりとなります。
① 治療を開始するのが遅れた
精神疾患には、「高熱が続く」とか「体が痛い」といった分かりやすい症状が出ないため、病気の発見が遅れ、そのため治療を開始するのが遅れる、その分、病気が進行する可能性が高まり,治療にも時間がかかる傾向にあります。
② 自己判断で薬の服用を途中で止めた
治療で薬を処方され、きちんと服用すると約6ヶ月から1年程度で症状が改善されていくことが多いのですが、この改善で「完治した」と錯覚してしまい、自己判断で薬の服用を止めてしまったり、気の緩みから飲むのを忘れてしまったりすると、再発する原因になり、治療も長びきます。
③ 身体疾病を併発している
例えば、糖尿病や心臓病など、慢性身体疾患を患っているとうつ病にかかりやすく、逆にうつ病患者は糖尿病などの慢性身体疾患にかかりやすいともいわれています。
うつ病と身体疾病はお互いに悪化させる関係にあるため、治療期間はうつ病のみの治療に比べると長くなりがちなのです。
④ 不安障害を併発している
不安障害にはいくつか種類があり、代表的なものに「パニック障害」「社会不安障害」「全般性不安障害」などがあります。
不安障害とうつ病などの精神疾患を同時に患った場合も、治療は長期化する傾向にあります。
中でも、突然手足が震えたり、呼吸困難になったりするパニック障害は、うつ病と併発しやすいのが特徴です。
焦らずにまずは治療を行ってください。
以上のように、精神疾患の治療には長期間を要することが一般的です。
自己判断で「治った」と思い込まないように、しっかりと医師と相談しながら治療を行ってください。
後遺障害が残った場合には、会社への損害賠償請求もあり得ます。
労災認定された精神疾患について、長い期間治療を行ったにもかかわらず完治せず、「症状固定」となった場合、後遺障害が残っているとして労災保険上の障害補償給付を申請することになります。
この障害給付が認められれば、慰謝料等について、会社に対して損害賠償請求を行うことを検討することになります。
会社に対する損害賠償請求は、一定の専門性を必要としますので、ぜひ弁護士まで、ご相談ください。
お一人で悩まずに、まずは、お電話ください【03-6277-8802】。
メールやLINEでも相談可能です。
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!