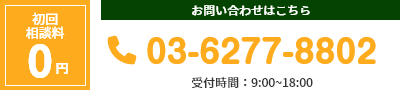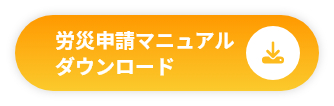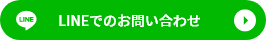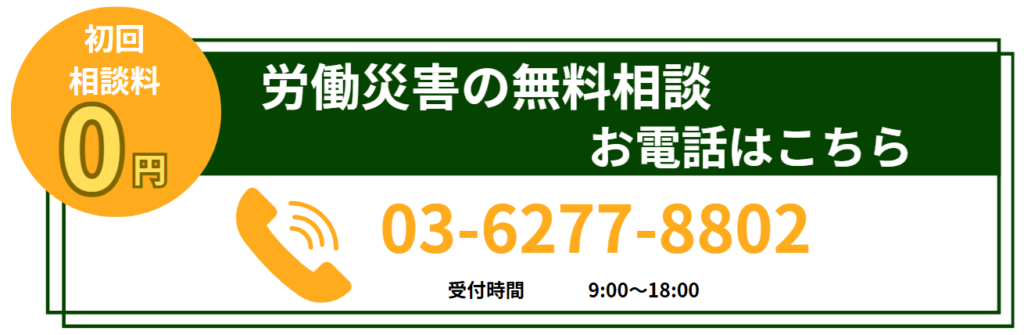休業補償給付とは
「休業補償給付」とは、労働者が業務上の事由によって怪我をしたり病気になり、仕事を休まなければならなくなった場合に労災保険から支給されるものです。
通勤災害の場合には「休業給付」といいます。
有給休暇を使わずに欠勤しても、この休業補償給付が受け取れるので、休業期間も安心して治療を受け続けることができます。
休業補償給付を受けるための3つの要件とは
休業補償給付を受給するためには、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
①労働災害(労災)に被災したこと
②治療のために労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
① 労働災害(労災)に被災したこと
まず労災に被災したことが必要です。
業務災害については、業務起因性と業務遂行性が必要となります。
② 治療のために労働することができないこと
労災に被災して、労働をすることができない状態であることが必要です。
休業補償給付は、労災によって仕事を休まざるを得ない場合の補償をするものであり、「労働をすることができない」状態である必要があります。
労働をすることができないかどうかは医師による判断が必要ですので、休業補償給付の申請の際には、医師に請求書の所定の欄に記載してもらうことになります。
③ 賃金を受けていないこと
賃金を受けていない場合である必要があります。
労災に被災して仕事ができなくなっている場合でも、会社の規定に従って賃金が支払われている場合もあります。
このような場合には、休業の補償をする必要はないため支給されません。
休業補償給付の補償内容とポイント
賃金の全額が補償されるわけではありません
「休業補償給付」は給付基礎日額(労災事故発生日の直前3ヶ月間の賃金を日割り計算した平均賃金)の60%が支給され、「休業特別支給金」は給付基礎日額の20%が支給されます。
そのため、合計で賃金の80%相当となります。
具体的な例を用いて、計算してみましょう
例:労災事故発生日の直近3ヶ月間の賃金の合計額は825,114円、その3ヶ月の総日数は92日、労災事故が発生してから30日間休業したケース
まず、労災事故発生日の直近3ヶ月間の賃金の合計を、その期間の総日数で除した金額である、給付基礎日額を計算します。
825,114円÷92=8,968.63円
給付基礎日額を計算する際、1円未満の端数は1円に切り上げて計算します。
そのため、給付基礎日額は、8,969円となります。
次に、休業補償給付金は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給されるので、次のように計算します。
休業補償給付金
8,969円×60%=5,381.4円
休業特別支給金
8,969円×20%=1,793.8円
1日当たりの休業補償給付の金額の1円未満の端数は切り捨てになるので、休業補償給付金は5,381円、休業特別支給金は1,793円となります。
その結果、1日当たりの休業補償給付の金額は、5,381+1,793=7,174円となります。
休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません(待機期間といいます。)
つまり、休業補償給付は、休業4日目から支給されるので、30日間休業しても、30日-3日=27日分しか支給されないことになります。
よって、今回のケースでは、支給される休業補償給付の金額は、
7,174円×27=193,698円となります。
休業補償給付の対象となる期間
次に、休業補償給付の対象となる期間を見てみましょう。
開始時期
休業補償給付の対象となる期間は、休業して賃金の支払いを受けられなくなった日の4日目からです。
1日目から3日目のことを「待機期間」と呼んでおり、土日祝日など会社が休みの日でも1日と計算します。
終了時期
休業補償給付の支給終了時期に制限はありません。基本的に労働者が再度働けるようになるまで支給されます。
ただし、ケガが完治しなくても症状が固定して治療を終了すると、休業補償の支給も終わります。
症状固定後に後遺障害が残った場合には、別途労働基準監督署に申請をして後遺障害認定を受け、障害補償給付を受けることができます。
年次有給休暇との関係
休業補償給付が受給できるケースでも、年次有給休暇を使うことは可能です。
上記のとおり、休業補償給付からは賃金の80%までしか支給されないので、年次有給休暇によって100%の賃金を受け取れればメリットはあるといえます。
しかし、休業補償給付の対象日を年次有給休暇として扱ってしまうと、休業補償給付の支給対象外になってしまいます。
年次有給休暇を利用するか、労災の休業補償給付を利用するかを慎重に検討する必要があります。
退職した場合の休業補償
労災事故当時に勤務していた会社を退職した後であっても、休業補償給付の要件を満たしているならば、引き続き休業補償給付を受給することができます。
退職後に休業補償給付の請求をする際、勤務先の会社の証明は不要です。
休業補償を受け取るための手続きについて
必要書類を労働基準監督署に提出する
休業補償給付は、必要書類を労働基準監督署に提出して請求します。
制度上は、労働者自身が労働基準監督署に請求書を提出して請求することが原則とされています。
しかし、労働者が労災請求を行うのが困難なときは、労働者の労災申請を手助けする義務(助力義務)が会社(事業主)に課せられています。
そのため、会社が請求を代行することも可能で、現実にはほとんどのケースで会社が請求を行っています。
会社が請求を行ってくれず、自分で行うことになった場合でも、請求をする際の請求書に「事業主証明欄」は会社に作成してもらうことになります。
必要な書類について
休業補償給付を請求するためには、「請求書」を労基署に提出する必要があります。
業務災害の場合には、休業補償給付支給請求書(様式第8号)
通勤災害の場合には、休業給付支給請求書(様式第16号6)となります。
これらの書式は、厚生労働省のホームページでダウンロードが可能です。
(主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html)
この請求書には、会社による証明と、医師による証明をもらいます。
休業補償を受け取るまでの時間
労基署に請求書を提出してから休業補償給付を受け取るまでには時間がかかることがあります。
これは、申請について審査をする必要があるからであり、最もスムーズな場合でも1ヶ月以上はかかるようです。
うつ病などの精神疾患や、過労による脳疾患・心臓疾患のように、業務と病気との因果関係の判断が難しいものについては、6ヶ月程度の長期間がかかることもあります。
休業補償にも時効はあります
休業補償給付は2年で時効にかかります。
ただし、休業補償給付の請求権は賃金を受けない日ごとに発生しますので、その翌日から2年が経過することにより時効期間が完成します。労災事故の日から2年ではありません。
休業補償では十分ではない場合も
休業補償給付によって、賃金の80%はカバーをすることが可能です
しかし、残り20%については休業補償給付では補償を受けることはできません。
足りない部分などについて、会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。
会社に対して損害賠償をできる場合とは
会社は、労働者に対して労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があります(安全配慮義務:労働契約法5条)。
この義務に違反して労働者が怪我や病気になった場合は、債務不履行として会社に対して損害賠償請求をすることができるのです。
また、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合にも、会社に責任が認められ、会社に損害賠償請求をすることができます。
会社に損害賠償を求める方法
会社に損害賠償を求める方法には次のようなものがあります。
交渉
会社に損害賠償の支払を求めて交渉を行います。会社が支払義務を認め、任意に支払ってもらえれば、解決ができます。
裁判
会社が損害賠償の支払に応じない場合には、裁判所に訴訟を提起することができます。
訴訟となると、どうしても時間はかかってしまいますが、裁判所による公正な判断を得ることができるというメリットがあります。
労災給付では補償されないものも会社に対して請求できる場合があります
会社に責任が認められる場合には、休業損害のほかにも、次のような損害について、会社に対して賠償請求が可能です。
慰謝料
労災に被災した場合、怪我や疾患を負ったことによる精神的苦痛を受けることになります。精神的苦痛に対しては慰謝料が発生します。
慰謝料には、怪我・疾患を負ったことで入院・通院したことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)と、後遺障害を負ったことに対する後遺傷害慰謝料があります。
しかし、労災保険からはどちらの慰謝料も一切給付されません。
そのため、会社に安全配慮義務違反等の責任が認められる場合には、会社に対して慰謝料請求をすることが可能です。
逸失利益
労災に被災して大きな怪我をした場合、後遺障害が残ってしまうこともあります。
その後遺障害によっては、以前のように働けなくなって、収入が落ちてしまうこともあるでしょう。
後遺障害のために、労災事故がなければ得られたはずの収入を失ったという損害を「逸失利益」といいます。
労災保険では、残った後遺障害に対して労基署が「障害等級認定」を行うので、障害等級の認定を受けると、労災保険から等級に応じた補償給付を受けることができます。
しかし、損害賠償として算定される「逸失利益」の金額に比べると、労災保険から受けられる障害補償給付額はだいぶ少ないことがほぼ常です。
そのため、会社に安全配慮義務違反等の責任が認められる場合には、会社に対して逸失利益の賠償請求をすることが可能です。
お一人で悩まずに、ぜひ弁護士にご相談ください
本記事では、休業補償給付とはどのようなものかを中心に、実は十分な補償を受けられていない場合についても合わせてお伝えしました。
賃金の80%を補填してくれる休業補償給付ですが、労災に被災した場合の損害のすべてを補填してくれるわけではありません。
会社に安全配慮義務違反等の責任がある場合には、会社に対しても損害賠償請求が可能となるので、まずは弁護士に相談してみてください。適正な補償を受けてくださることを私は望みます。
労災に遭ってしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
初回相談は無料です。
お一人で悩まずに、まずは、お電話ください【03-6277-8802】。
メールやLINEでも相談可能です。
依頼者の皆様にとって最善の解決に至るため、当事務所は、これまで培ってきた他事務所の弁護士や他士業の方々との幅広いネットワークを有効活用し、ベストを尽くします!